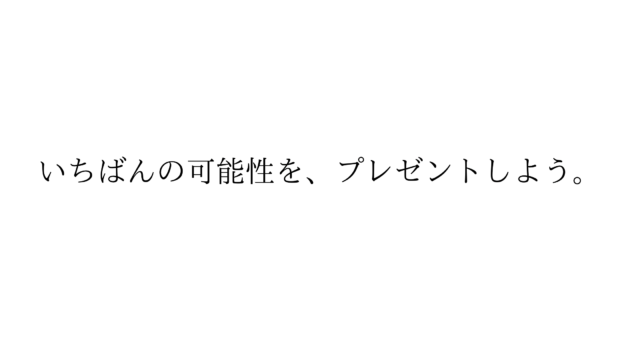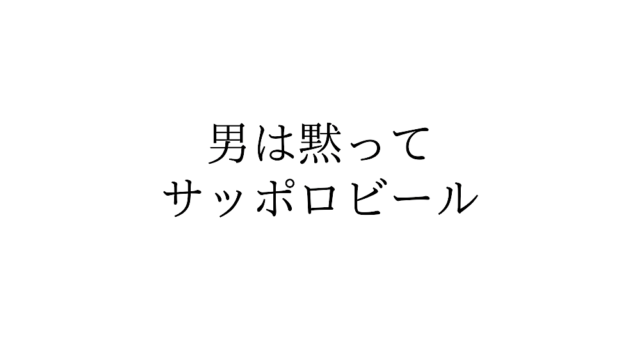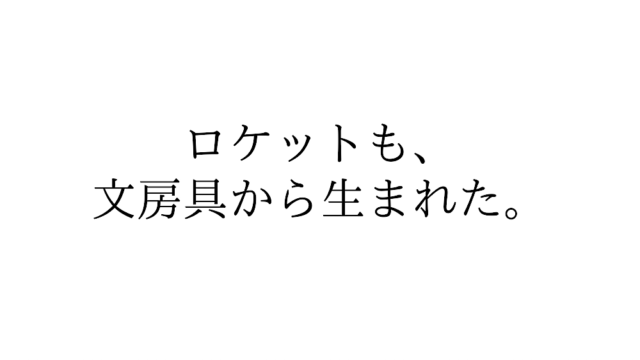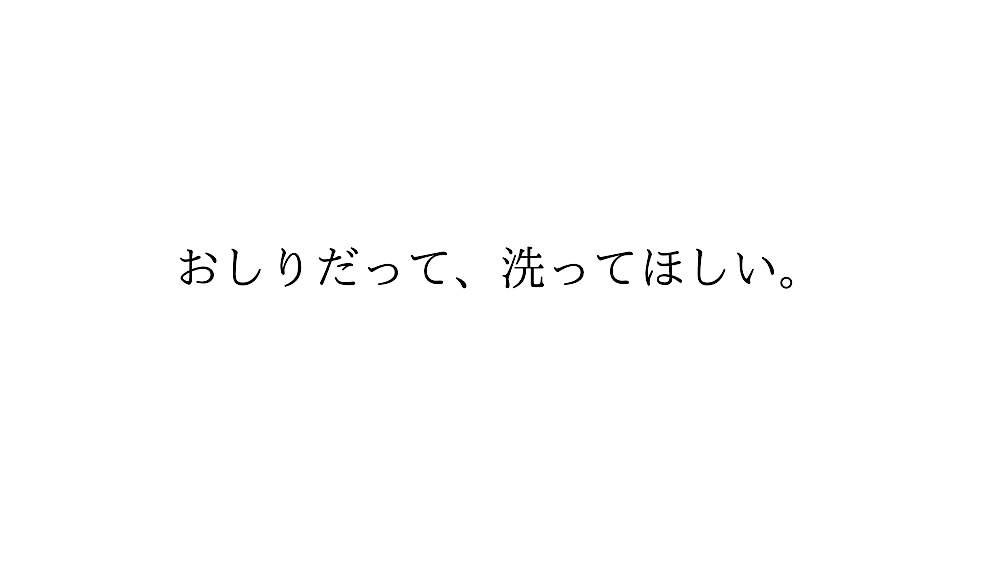
前回記事で、家族のシーンが描かれたトイレ関連のコピーがパッと浮かばないというような余談をしました。
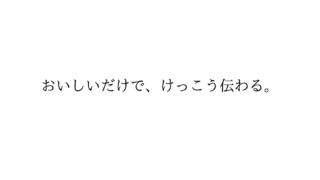
…が、その直後に、あの名作コピーを思い出しました。そしてトイレという空間に関しては、もはや〝家族〟というより人間という〝生き物〟としての文脈のほうが強いからだと腑に落ちました。それがこちらのコピーです!
おしりだって、洗ってほしい。
1983年 東陶機器 仲畑貴志
今や当たり前に使っているウォシュレットの広告コピーですね。
ぼくは外出先でトイレに行きたくなったとき、そこにウォシュレットがついてなかったら、トイレを見送るほど依存しています。
「ちょっと、ウ◯チしたいなぁ」という不誠実で不純なノリだったら、間違いなく見送ります。というか、ウ◯チのほうからスッと引っ込んでちゃんと自粛するくらいです。
ウォシュレットのないトイレなんて、インターネットにつながってないスマホのようなものだと思ってます。
これまで、〝拭く〟ことが当たり前だった時代に〝洗う〟ことを提案したウォシュレット。大袈裟じゃなく世界を、人間を進化させた大発明だと思っています。
おしりは「拭くだけ」という常識からの脱却。
発明がすごいことはもちろんですが、生活者に〝おしりを洗う〟という気づきを与えて、習慣にさせたコピーの影響は非常に大きいです。ぼくはここに言葉の力や偉大さを感じずにはいられません。
というのも、実はウォシュレットはTOTOが販売した1980年代より前、1970年代にすでにINAX(現LIXIL)が開発し、サニタリーナという名前で販売をしていたそうなんです!
10年も前から開発・販売をしていたINAX(現LIXIL)が、なぜTOTOに遅れを取ってしまったのか?
それがまさしく、言葉の力だったとぼくは思います。
ご存知の方も多いと思いますが、ウォシュレットという名称はTOTOの登録商標。正しくは、温水洗浄便座です。これを当時のTOTOの宣伝課長さんが「これからはおしりは洗う時代だ!さぁ洗おう!」と呼びかける「レッツ・ウォッシュ」を逆さにし、ウォシュレットと名付けた逸話があります。まず、このネーミングにもキャッチーさがあって親しみやすいですよね。ここにも、言葉の力が秘められています。
そして、なにより強く世間に影響を与えたのは「おしりだって、洗ってほしい。」というコピーでしょう。
外出先で手や顔が汚れたら、まず水で洗い、そして拭いていた。なぜ、おしりには〝洗う〟という手順がないのか?
今の時代を生きる人からすると、当時それを疑問に思っていた人が少数(心の奥ではなんとな〜く思ってた程度)だったことに、驚きですよね。
このコピーをみると、〝疑う〟という姿勢は〝クリエイティブの基本〟なんだなぁと思わされます。
〝だって〟という言い回しがポイント。
このコピーも言い回しひとつで、本当に印象が変わります。
「おしりも、洗おうよ。」
「おしりも、洗ったほうがいいですよ。」
「おしりも、洗わなきゃダメだよ。」
これだと、広告側の一方的なメッセージになっていて気づきが得られない。
「おしりも、洗ってほしい。」
これも、商品を販売する側の都合が入っててちょっと弱い。
「おしりだって、洗ってほしい。」
やっぱり、〝だって〟という言葉が入ることで非常に効いてきます。
みんな心のどこかで気になってたんだけど、見て見ぬふりをしていた〝おしり〟の存在に注目がいく言い回しです。「ああ〜!ごめん、おしり!そうだよね、おしり!!」って、なる感じです。
いくら優れた商品でも、生活者がその価値に気づかなきゃ広まらない。生活者の気づいていない欲望を、言葉でスッと拾いあげることで広まっていく。最も流通している〝言葉〟だからこそ、できることですよね。広告コピーの役割として、非常にわかりやすい事例だと思います。
愛嬌とチャーミングさの重要性。
ちなみにですが、TOTOがシェアを獲得していくなかで、INAX(現LIXIL)はシャワートイレという名称で再度、販売にチャレンジしたそうです。結果は言わずもがな…。
広告には〝愛嬌〟とか〝チャーミングさ〟も大事といわれますよね。
そもそもシャワーとトイレって、言葉の組み合わせがマズイと思います。
シャワーは頭から全身を流すイメージで、トイレは排泄をイメージしてしまう。なんか、トイレの水を浴びるイメージになっちゃう気がします。すでにウォシュレットを知っている人間の先入観がある見解ですが、生理的に受けつけられない感じがしますよね。
「おしりだって、洗ってほしい。」
商品を売ること、新しい生活を生み出すことに、〝言葉〟の力が偉大であることひしひしと感じるコピーです。